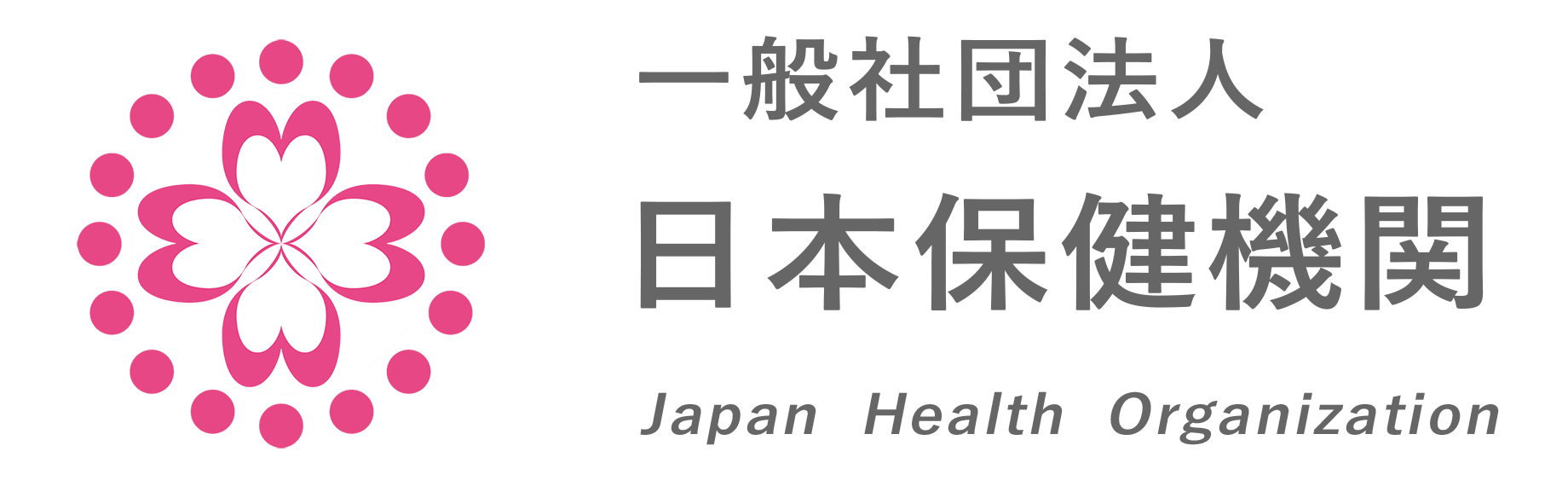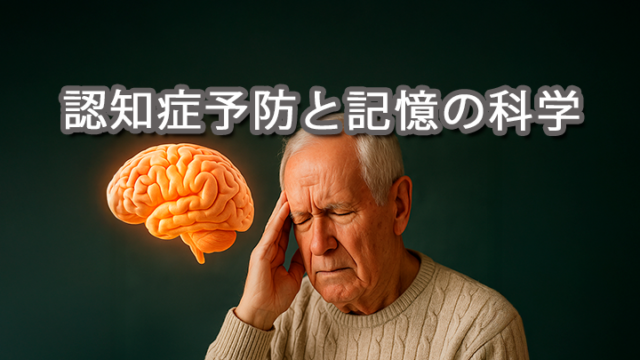体内のオートクリーニングとリセット
人の体を構成する約37兆個の細胞は、日々代謝(生命活動)を続け生命を維持しています。細胞の中ではエネルギーや体の素材など、生命維持のために必要なものがつくられています。その過程では、不要な老廃物(ごみ)が発生します。このごみの処理がスムーズにできず細胞内に蓄積すると、細胞機能が低下し健康維持ができなくなります。そこで細胞内にごみをためずクリーニングし、リセットするシステムがオートファジーです。
オートファジーは、細胞が飢餓状態に直面した時に活発になります。クリーニングをする役割だけでなく、外から栄養を摂れないときには自らを分解して生命維持をすることもあります。
高等動物においては、栄養が満たされた状態においても健康体であればオートファジーは基底レベルで起こっています。消化器が休止状態にあると、オートファジーが細胞内成分を代謝することにより常に細胞内を浄化しています。
オートファジーの解明
オートファジーは、1960年代に細胞内のリソゾームでその現象が確認されていたましたが、その分子メカニズムは長い間解明されていませんでした。その解明に貢献したのが、生物学者の大隅良典博士(1945~ )です。大隅博士はオートファジーの仕組みを解明した功績により、2016年のノーベル医学生理学賞を受賞しました。
オートファジーが注目されるのは、生存に欠かせない仕組みであるという理由だけでなく、多くの病気、感染症の予防、免疫応答などに深くかかわっていることが分かってきたからです。
空腹時にオートファジーがスイッチON
マウスの実験では、絶食させ細胞が飢餓状態におかれると、12~24時間後にオートファジーの活動が最大になることが確認されています。人の場合は、約16時間後といわれています。
人が飢餓状態に陥ったとき、しばらくの間は蓄積した脂肪を分解してエネルギーにします。その間オートファジーは、細胞内のクリーニングに集中します。蓄積した脂肪がなくなったときは、細胞内の不要なものから順に分解しエネルギーに変えて生きていきます。この時、菌やウイルスでさえ分解してエネルギーに変えてしまいます。
病気治療にもオートファジー
◇感染症防止
ウイルスや菌などが体内に侵入した時、オートファジーが働いて細胞内へ進入した菌を捕食・処理します。
免疫細胞のマクロファージや好中球などの食細胞が、体内に侵入した異物や病原体を小胞に包んだ形で取り込み異物を分解・排除します。しかし細菌中には、貪食の機構から逃れる能力を持つものもあります。オートファジーは免疫細胞から逃れた細菌も再び捕えなおして分解する働きも果たしており、体を微生物から守っています。
◇認知症防止
脳内でオートファジーが十分に機能することができないと、細胞の中に異常タンパク質(アミロイドβタンパク)の塊りができて認知症を引き起こします。
◇肝臓障害
オートファジーにより肝臓の炎症細胞が分解され、新生細胞に入れ代わります。
絶食時における糖新生に肝臓のオートファジーが重要な役割を担います。
◇腫瘍抑制
オートファジーには腫瘍(癌)抑制効果があり、癌を予防する可能性があります。異常細胞ができた場合、これを分解してリサイクルすることによって、腫瘍が増殖していくのを抑えることが考えられます。
◇その他
腸、腎臓、心臓、血管、自律神経、内分泌(ホルモン)、免疫機能など、あらゆる病気の
予防・改善につながります。
オートファジーを日常に活かす
日常的に、オートファジー機能が十分発揮される生活を送っていると、疲労防止、老化防止、認知症をはじめあらゆる生活習慣病の予防につながります。
そのためには、過食・飽食を避け、間食を控え、シンプルな食事にすることです。過度の負担を内蔵に与えないために、加工度の高い食品、農薬が多く含まれるもの、動物食品などは、極力控えることです。
オートファジーのスイッチが入るには、少なくとも16時間の絶食が必要です。したがってベストは夕食1食、次が昼夕の2食です。お腹を空にしておく時間が長いほど、体内クリーニングと体内リセットが円滑に行われます。