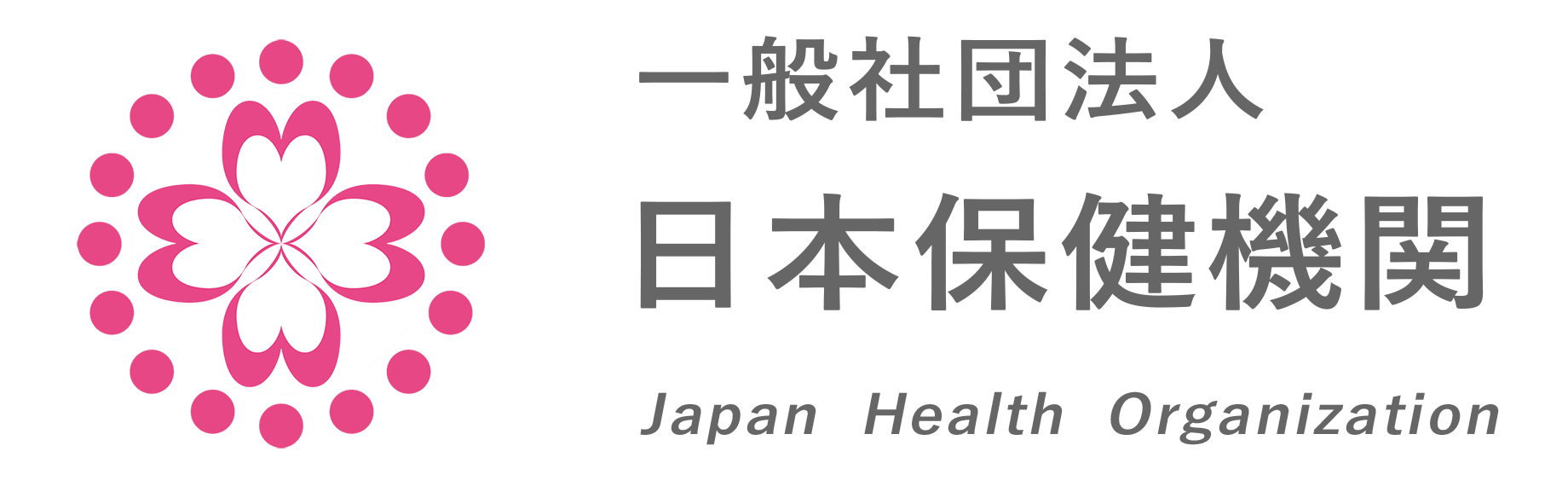脳と腸の深い関わり『脳腸相関』
生物は進化の過程で、海水から栄養分を吸収するためにその構造を進化させていきました。やがて、より効率的に栄養を吸収できる“管”の構造が、生物が初めて獲得した内臓器官である”腸”の原型でした。そして脳は、”腸”を動かすための神経細胞が進化したものと考えられ、脳と腸は生物誕生の時から密接な関係にあります。腸には脳と直接つながる神経は少ないにもかかわらず多くの神経細胞が存在し、これらは食物に反応してぜんどう運動の調節や消化管からのホルモンの分泌調節を行っており、脳とは独立した活動です。
腸は独自の神経ネットワークを持っており、脳からの指令が無くても独立して活動することができるため「第二の脳」ともよばれます。たとえば腐ったものを食べた時に吐いたり、下痢を起こしたりするのは腸が自ら危険を察知して反応した結果です。
たとえばストレスを感じるとお腹が痛くなり、便意をもよおすことがあります。これは脳が自律神経を介して、腸にストレスの刺激を伝えるからです。逆に腸に病原菌が感染すると、脳で不安感が増すとの報告があります。また脳で感じる食欲にも、消化管から放出されるホルモンが関与することが示されています。これらは、腸の状態が脳の機能にも影響を及ぼすことを意味しています。最近では病原菌だけではなく、腸内の常在菌も脳の機能に影響を及ぼすことによって心や身体に影響することが明らかになりました。
腸から摂食中枢を刺激するホルモンが放出されると、脳は食欲を感じます。逆に腸から満腹中枢刺激ホルモン(GLP-1)が分泌されると食欲が抑えられ、少量の食事で満足することができるようになります。
このように生物にとって重要な器官である脳と腸がお互いに密接に影響を及ぼしあうことを「脳腸相関」と言います。
脳腸相関と病気の関わり
過敏性腸症候群においては、腸内細菌の異常により、腸から脳への信号伝達(内臓知覚)に異常が生じているようです。
腸内に神経伝達物質(ガンマアミノ酪酸)を産生する菌が少ない子供は、行動異常、自閉症などが起こりやすくなります。
緊張した時や、ストレスが強くかかる状況でおなかが痛くなり、トイレに行きたくなることがよく起こります。また新シーズンで学校や職場が変わった時、旅行中などでは便秘を経験することも多くあります。これは脳が精神的なストレスを感じると自律神経を介してぜんどう異常という形で腸にストレスを伝達しているからです。逆に腸の不調は、脳に伝わり症状の悪循環を引き起こし、下痢や便秘の症状を悪化させるため、「過敏性腸症候群」が起こると考えられています。過敏性腸症候群 は、消化管のぜんどう異常、消化管の知覚過敏といった消化管での問題と情緒不安定といった心理的な要素が原因となる脳腸相関と深く関わる病気と考えられています。
脳内で情動のコントロールに関わる神経伝達物質として作用しているセロトニンは、その大半が腸で作られており、腸のぜんどう運動の調節にも関わっています。
腸内フローラは幼児期に決まる
腸内細菌には、有用菌(善玉菌)と悪用菌(悪玉菌)が共存しています。腸内フローラ(菌郡)の種類の大部分は生後10ヶ月位までに形成され、1歳半位までの食生活で大方は決定されます。その後も腸内細菌の種類は変わらず、バランスや量の変化は体調をはじめ多くの因子の影響を受けて変化します。
人の脳は、乳幼児期に集中して発達・形成されます。その時の腸内細菌の状態は脳の形成に大きな影響を与え、その時期に形成された脳によって後の性格や健康状態が左右されます。
成長期から成人になる過程における悪用菌(悪玉)を増やす要因は、不調和な感情、ストレス、化学物質(抗生剤、化学添加物、農薬など)、高脂肪食、環境汚染などです。
腸内細菌と病気の関わり
近年、腸と他の病気の密接な関係が次々と明らかになりました。以下は、近年の研究報告です。
- 腸の組織以上に、主となる影響力は腸内細菌である。
- 腸内細菌は、人の理性や人格さえも左右する可能性が高い。
- 人の遺伝情報(ヒトゲノム)は、腸内細菌に支配されている。
- 脳が正常であっても、腸の機能障害や腸内菌のアンバランスによって理性の働きが失われることがある。
- 乳幼児期に抗生物質を使用すると、腸内菌が死滅して菌のバランスが乱れるという大きなリスクを伴う。
自閉症は、生後18か月以内に抗生物質の治療を受けるのは最大のリスクとなる。
アレルギーに関しては、2歳になるまでに抗生物質の治療を受けた子供は、後に喘息、アトピー性皮膚炎などのアレルギーを発症する率が通常の2倍も高くなる。
抗生物質を多く与えられるほどアレルギー体質になりやすく、4クール以上の治療を受けた子供は3倍もアレルギーを発症しやすくなるという結果が出ています。
破傷風菌の繁殖を阻止する腸内菌類を抗生物質で殺してしまうことで、破傷風菌が繁殖しやすくなる。その結果、破傷風菌類が腸内で繁殖して毒素を出し、それが脳に到達して自閉症になるケースがある。
- 腸機能の障害や腸内細菌の消失が、様々な精神障害(統合失調症、後発型の自閉症など)を発症するケースが多くある。
- 感染症を起こす病原体の細菌は身体だけでなく、精神にまで影響を与えることがある。
ラットがトキソプラズマに感染すると恐怖心を失って振る舞いが変わり、猫に向かって行って食べられてしまうことがある。猫好きの人が猫にひっかかれることでトキソプラズマに感染し、性格が変わることもある。
微生物と人は共存
微生物はそれぞれ独自の特質があり、生成・分泌する物質は様々な作用があります。人類の長い歴史の中で共存共栄の関係を保ってきた微生物は、人に恩恵を与える有益な存在であったのです。
共存関係の微生物は、人の身体の内外に存在して互いに助け合いながら暮らしています。外界の食物や環境中にも存在して、人との共存関係を保っています。微生物なくしては、人は生きていくことができません。微生物は、無限の可能性を秘めています。