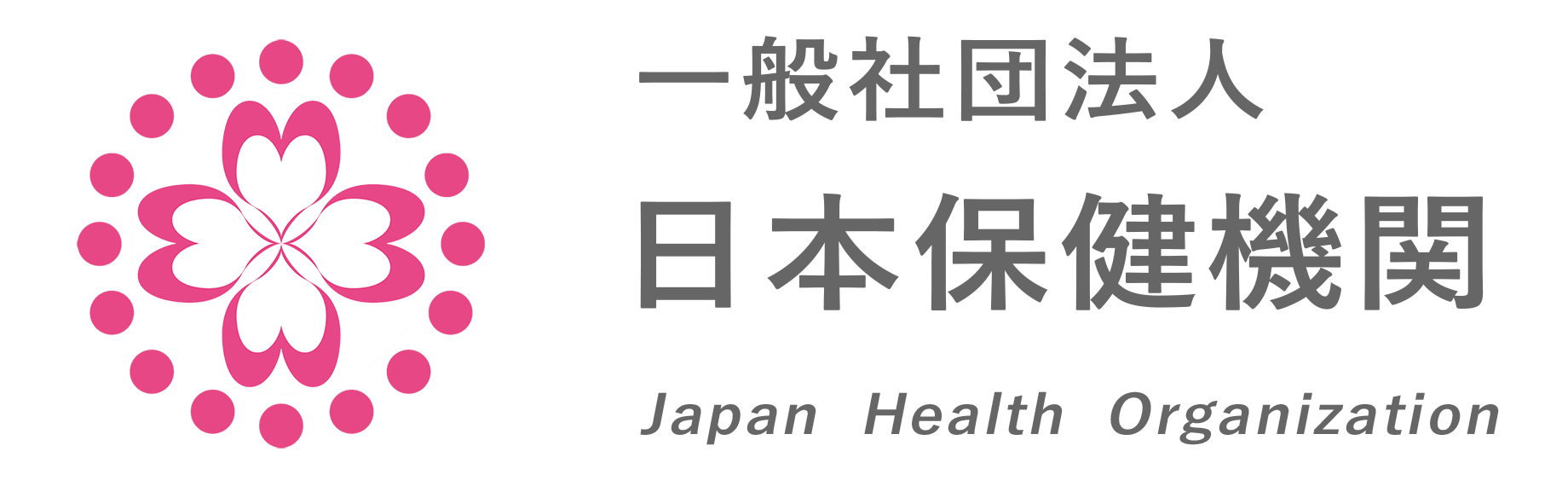老化とは
人生における煩悩は、『生老病死』に集約されます。このうち老いる苦しみは、加齢とともにすべての機能が衰え、苦しみの内にこの世から去っていくことが当たり前のように思われています。古今東西、数え切れないほどの人々が不老長寿の術を探し求めてきましたが、手にした人は一人もいません。現在でも世界中の人々が老化のメカニズムを究めようとしていますが、人を細分化して部分的に捉えようとするかぎり答えを得ることはできないでしょう。
人がこの世に生まれてから25年がピークで、そこからは老化の一途をたどっていくことになります。脳をはじめ、神経細胞、皮膚、歯、目、耳、骨、血管など、体を構成するすべての器官が衰えてきます。
長い間自然法則に反した生活をしていると、臓器・器官に徐々に代謝産物(疲労物質、老廃物)が蓄積し機能が衰えてきます。さらにエスカレートすると器官の細胞は変性や破壊が起こってきます。全身器官が同時に低下してくるので、特定の病気ではなく症候群のように複合した状態になります。それを年のせいにするのが人の常ですが、自らの生き方の反映であると知るべきです。
人体は、37兆個の体細胞と血液細胞で構成され、互いが絶妙な連携のもとで機能しています。老化現象は、細胞レベル・分子レベルで全身の機能低下が起こってくる慢性疾患です。細胞の機能が低下するのは、細胞の代謝が円滑に行われないためです。細胞の代謝が円滑に行われるための主要な条件は、細胞の環境です。細胞の環境とは、細胞の周囲を常に循環している体液です。体液の質と循環が常に健全であれば、細胞は健全に機能することができます。体液の元はすべて血液であり、体液を良質にするには血液の質を良くしておかなければなりません。血液の質は、食物の質とイコールです。したがって食生活を調えて良質な血液をつくることが、老化防止の重要な要になります。
老化は生活習慣病(慢性病)
老化はだれにでも起こる全身的機能低下現象であり、避けられないものと思われています。これは誤った認識であり、人は本来生涯現役で、この世にいるかぎりは元気で快適に生きることができる構造になっています。それが途中で故障を起こすのは使用法が間違っているからです。正しい体の使い方をしていれば、いつまでも故障なしで活動できるものです。したがって老化は高齢になれば必ず起こるものではなく、生活の誤りの積み重ねで発生する病気ということです。
老化は慢性病という考え方は近年注目されており、WHO(世界保健機関)の国際疾病分類(ICD-11)でも、老化は疾病として位置づけられています。
生涯現役
人は年を重ねるにしたがって肉体も頭脳も衰えてくるのが当たり前で、だれも避けることはできないという固定観念が潜在意識にこびりついています。誤った固定観念が潜在意識の奥深くに信念のように定着しているのです。潜在意識の中に強く固定している意識は、そのとおりのことが現実となって現れるのが人のしくみです。その誤った自己像を造り変えないかぎり、自ら望まない自分を造り出し現実となって顕現します。
人は、心身の適切な使い方をしていれば、肉体機能は一生維持され、脳機能はどこまでも進化・向上し続けて、生涯衰えることはないものです。『生涯現役』という意識を強くもって生きていくことが大切です。